OJTの理論&手法 :
OJT Tips
OJTのツールを整備する(2)
公開日:2025年04月01日
「OJTのツールを整備する(1)」でOJTを効果的に運用するためのツールを分類しました。今回は、シート類について解説します。
計画と進捗管理のためのツール(シート類)
OJT計画書について
OJTでは、もともと計画性が非常に重視されています。そのため、OJTを行う際には実施内容と日程スケジュールを含んだ「OJT計画書」が必須とされた時期があります。
確かに場当たり的な指導とならないようにするためには、「計画書」はあったほうがよいでしょう。しかし、指導担当者にとっては、この「計画書」作りが大きな負担となっていました。
例えば、3カ月間のOJT計画を作ろうとしても、仕事の予定が3カ月先まで見通せている職場はあまり多くありません。そのため、指導の計画を考えること自体が難しく、何とか計画は組めたとしても、かなりの確率でズレが生じてしまいます。
計画と実際のズレが激しいとOJTに対するモチベーションを下げてしまい、遅れを指摘されたり計画書の修正を強要されたりすると、いよいよ苦痛ばかりが増えてしまいます。少し極端ではありますが、これらの状況を捉えると、「OJT計画書」を重視したことがOJTを阻害していたようにも思えてきます。
シートを設計する際の視点
しかし、OJTを計画的に進めること自体の重要性は否定できません。そのため「計画」に対する考え方を見直してみる必要がありそうです。
例えば、指導担当者がOJTの指導予定と仕事が重なった場合、仕事を優先するのが普通の選択のはずです。そうなると、OJTのほうは仕事の合間を縫って、常に臨機応変に進めていくことが求められます。
こうしたOJTのあり方を現実的に検討し、それを反映した書式に工夫していくことがOJTのシートを設計するうえで重要な視点となります。
言うまでもなく、OJTのシートはそれ自体が目的ではありません。あくまでOJTを効率よく進めていくための道具でしかなく、計画と進捗管理さえできれば、記入箇所は少ないほどよいです。そこで共通部分はあらかじめ埋めておいたり、再利用を可能としたり、記入欄を集約して必要最低限の内容にしていくなど、思いつく工夫はできるだけ取り入れましょう。
しくみ別のシートの例
新入社員のOJTの場合は、配属時点の能力がどうあれ、全員ゼロから一定レベルまでを指導していきます。そのため指導計画を個別に作る必要性は低く、職種ごとに1つずつ準備されたものを用いることができます。また指導項目は細かく多岐にわたるため、詳細なスケジュール計画を作るのは非効率です。
そこで、「指導項目の一覧」と月単位の大まかな「期間計画」だけを準備するようにします。「指導項目の一覧」には、項目ごとの指導の優先順位を付け、チェック欄として「実施」と「習得」の欄を設けておきます。「期間計画」のほうは、その期間の「テーマ」「内容」「イベント」「課題」などの記入欄があるとよいでしょう。
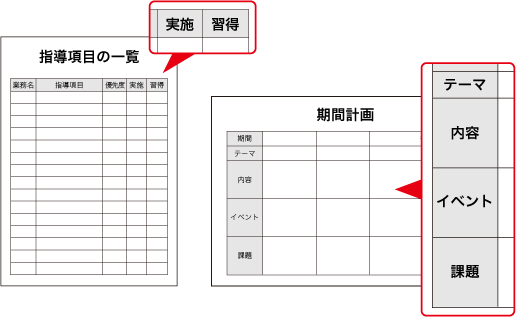
また、目標管理制度を利用したOJTでは、目標シートを作ることが重要なため、OJTのためのシートはなくても構いません。そのかわり、管理者用の「ワークシート」を準備し、どういう部分を伸ばすのかといった構想を練ったり、何を狙って課題を与えたかを記録したり、期中の指導ポイントをメモ書きできるようにしておきます。こちらは個人別のシートではなく、部下全員を一覧できるものが使いやすいでしょう。このようにOJTの「シート類」は、それぞれのしくみに合うものを工夫することが、OJTを活性化するための重要なポイントだと言えます。
なお、当社ではこれらの内容を踏まえて「OJT計画書」のシートを開発し、『OJT実践ノート』で紹介しています。ぜひ、お役立てください。
次回は、指導手順書について掘り下げて考えていきます。
- OJT Tips
- OJTのツールを整備する(4)
- OJTのツールを整備する(3)
- OJTのツールを整備する(2)
- OJTのツールを整備する(1)
- 友達感覚になっている新人への対応
- ミスの多い新人への指導
- 新人とのかかわり方
- 計画倒れにならない「OJT計画」のために
- 配属部署で行う準備:後編
- 配属部署で行う準備:前編
- 人事部門が行う準備:後編
- 人事部門が行う準備:前編
- 忘れられがちなこと
- 推論のはしご
- 新入社員の活性度別に見た対応
- シングルループ・ダブルループ学習
- 入社後2~3年の一般社員に対するOJTのポイント
- アサーティブな対応
- 個人内評価
- 肯定的ストローク
- 導入研修での実施項目
- ビジネスマナーの定着
- 新入社員への承認
- OJTリーダー養成研修のポイント
- 新人に「やらせる」ためのポイント
- 続ける・やらせる・鍛える
- OJT期間がいつまでか「決まっていない」場合
- 新人の指導担当者は誰にするか?:後編
- 新人の指導担当者は誰にするか?:前編
- 新入社員、早く育てる? 大きく育てる?
- リモートワーク環境でのOJTのために
- OJTでの質問リストの活用
- 在宅勤務の新人にオンラインでOJTする場合の留意点
- OJT計画の期間設定
- OJT計画の概要と考え方
- 新人受入の際の所属長の役割(配属日前の確認)
- 新人の役割を決めるための着眼点
- 新人のOJTにおける所属長の役割
- トレーニーのレベルを確認するための質問
- 質問の投げかけ方
- OJTのレッスンプランをつくる
- 新入社員のOJTと中堅社員のOJTの違い
- OJTとは?定義と関連用語
- 新入社員のうちにぜひ教えてほしいこと
- 内発的動機づけを高めるために
- 「意欲」の要因
- インストラクションの基本
- 新人に実務を割り当てる場合の留意点
- 新人の状態を観察するポイント
- まず自分の傾向を知る
- 理解のための切り口
- 知識と言葉
- 学習と記憶のメカニズム
- 新人の指導(マナー・ルール)
- 新入社員OJTのモデルプラン
- OJTの主な対象者と指導ポイント
- 定年延長や成果主義は若手の育成を妨げるのか?
- 日本企業のOJTは行き過ぎたマイナス文化なのか?
- OJTコーナーについて
- OJT概論



